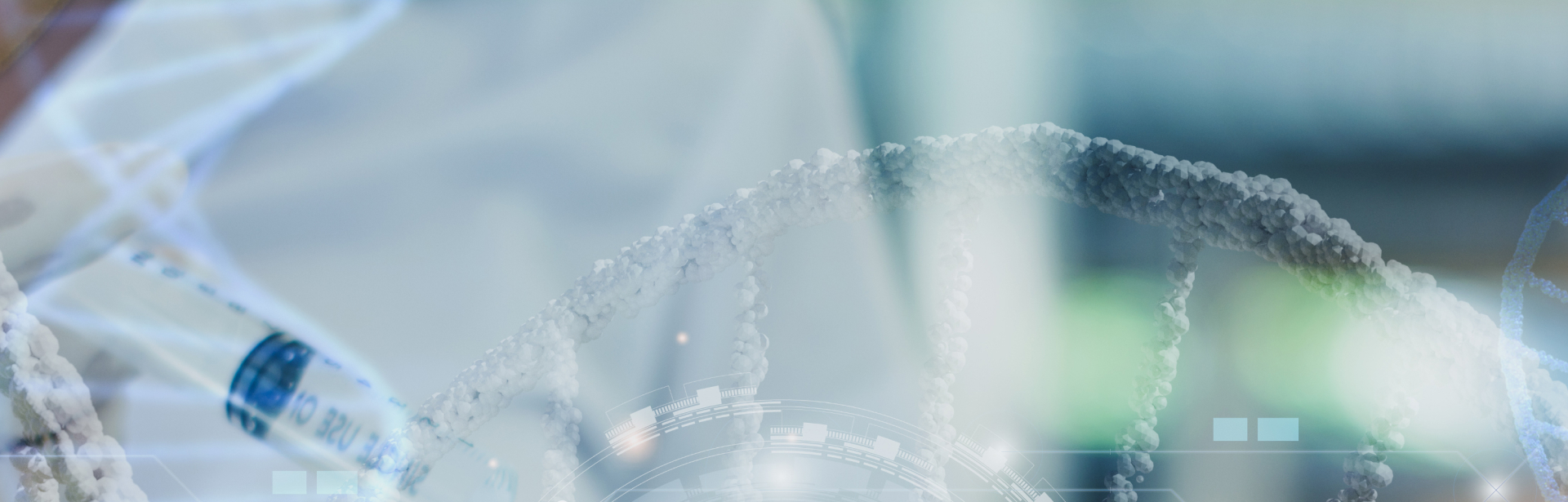大腸がん
当科では、大腸がんに対して最新のエビデンスとゲノム情報に基づいた個別化医療を提供しています。
国内外の治療ガイドラインを参考にしつつ、患者さん一人ひとりの病状や希望に応じた最適な治療方針を立案しています。
1.進行・再発大腸がんに対する薬物療法
進行・再発例では、下記のような標準治療を基本としつつ、腫瘍のバイオマーカーに応じた治療選択を行います。
標準的な治療法
- 細胞障害性抗がん剤
- 5-FU、オキサリプラチン、イリノテカン
- 分子標的薬の併用
- 抗VEGF抗体(ベバシズマブ等)
- 抗EGFR抗体(セツキシマブ等)
バイオマーカーに応じた治療選択
- BRAF V600E変異陽性例
→ エンコラフェニブ ± ビニメチニブ+セツキシマブ - MSI-High(高頻度マイクロサテライト不安定性)例
→ 免疫チェックポイント阻害薬(ペムブロリズマブ、イピリムマブ+ニボルマブ)
2.術後補助化学療法(アジュバント療法)
Stage IIIや再発リスクの高いStage IIの患者さんには、手術後に再発予防を目的とした補助化学療法を行います。
▼使用される主なレジメン
| レジメン名 | 構成薬剤 | 特徴 |
|---|---|---|
| FOLFOX療法 | オキサリプラチン+5-FU | 標準的な静脈内投与レジメン |
| CAPOX療法 | オキサリプラチン+カペシタビン | 経口薬併用により外来でも実施可能 |
| 経口単剤療法 | フッ化ピリミジン系薬剤単独 | 高齢者や有害事象リスク高の方に適応 |
治療効果と副作用のバランスを考慮し、個々の患者さんに最適な治療法を選択します。
多職種連携による集学的治療体制
当院では、腫瘍内科、外科、放射線科が連携し、集学的治療(multidisciplinary treatment)を行っています。
特徴
- 毎週の合同カンファレンスで症例を多角的に評価
- 手術、放射線療法、薬物療法を組み合わせた統合的治療戦略を立案
- 必要に応じてがんゲノム診療科や緩和ケアチームとも連携
この体制により、局所進行例や再発例でも高い治療効果とQOL維持を目指しています。
患者さん・ご家族へのメッセージ
治療法が多岐にわたる大腸がんでは、正確な診断と最適な治療選択が非常に重要です。
当科では、経験豊富な医師・薬剤師・看護師・多職種スタッフがチームで対応し、安心して治療に取り組んでいただける環境を整えています。
ご不安な点や疑問がある場合は、いつでもご相談ください。
胆道・膵臓癌
胆道がん・膵臓がん(総称して「胆膵がん」)は、早期発見が難しく、進行した状態で発見されることが多いがんです。
また、手術後も再発リスクが高く、難治性がんの代表とされています。
当科では、こうした胆膵がんに対し、標準治療と個別化医療を両立させた治療戦略を実践しています。
1.薬物治療の役割と進化
胆膵がんにおける薬物治療には、次のような重要な役割があります。
- 病状の進行を抑える
- 症状を軽減し、QOLを向上させる
- 手術前後の再発予防
以前は治療の選択肢が限られていましたが、近年のがんゲノム医療の発展により、患者ごとの遺伝子変異に基づく個別化治療が可能となってきました。
2.胆道がんの治療
標準治療の例:
- ゲムシタビン+シスプラチン(GC療法)
- S-1(テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤)
- 免疫チェックポイント阻害薬(デュルバルマブ、ペムブロリズマブ)
遺伝子異常に応じた個別治療:
胆道がんでは、FGFR2融合、BRAFV600E、NTRK、RET変異、MSI-High などが見られることがあり、
それらに対応する分子標的薬・免疫療法が選択されることがあります。
3.膵がんの治療
標準治療の例:
- ゲムシタビン+ナブパクリタキセル
- FOLFIRINOX療法(5-FU+レボホリナート+イリノテカン+オキサリプラチン)
遺伝性・遺伝子変異への対応:
- BRCA1/2変異陽性 → プラチナ製剤反応後にオラパリブ(PARP阻害薬)を使用
- KRASなどの変異も解析対象に
4.包括的な治療体制とサポート
当院では、以下のような多職種連携体制を整えています:
- 合同カンファレンスの実施(消化器内科・肝胆膵外科・腫瘍内科・放射線科)
- がんゲノム診療科との連携(がんゲノムプロファイリング検査とエキスパートパネルによる治療方針決定)
- 緩和ケア専門職(薬剤師・看護師・心理士・MSW)との連携によるQOL支援
患者さんへ
胆膵がんは決して簡単な病ではありませんが、早期の診断と、正確な治療方針の決定が鍵となります。
当科では、専門性と多職種の力を集結し、最善の治療と支援を提供いたします。
どんな小さなことでも、ご相談をお待ちしております。
口腔癌
口腔がんは全がん種の1〜5%と比較的稀ながんですが、食事や会話といった日常生活に直結する重要な部位に発生するため、生活の質(QOL)に与える影響が大きい難治性疾患です。
東京科学大学は、全国でもトップクラスの口腔がんの症例数が集結され、手術・放射線・薬物療法を組み合わせた集学的治療を行っています。
1.標準治療:まずは手術療法
切除可能な場合、手術が第一選択肢となります。これは早期診断・早期治療により、根治が期待できる標準治療です。
2.薬物療法の役割(再発例・切除困難例)
以下のような症例に対して、薬物療法が中心となります:
- 再発症例や遠隔転移例
- 解剖学的・全身状態的に切除困難な症例
- 放射線治療不適応例
近年では、免疫チェックポイント阻害薬(ICI)がこのような状況における標準治療として位置づけられています:
- ペムブロリズマブ(抗PD-1抗体)
- ニボルマブ(抗PD-1抗体)
3.多職種・多診療科による包括的対応
当院では、口腔がん診療において以下の密接な連携体制を敷いています:
連携診療科
- 口腔外科(顎口腔腫瘍外科学分野)
- 頭頸部外科(耳鼻咽喉科・頭頸部外科)
- 放射線治療科
多職種チームによるサポート
- 腫瘍内科医、歯科医師、看護師、薬剤師、臨床心理士、医療ソーシャルワーカー など
- irAE(免疫関連有害事象)に対しては迅速かつ学際的に対応
これらのチームは定期的な合同カンファレンスで症例を共有し、診断から治療方針決定、経過フォローに至るまで一貫して対応しています。
患者さんへ
口腔がんの治療は、がんの制御だけでなく、機能と見た目の回復、生活の質の維持が重要です。
私たちは、日本有数の大学病院における症例数と専門性を活かし、患者さん一人ひとりに最適な治療と支援を提供いたします。
どうぞ安心してご相談ください。